生物科学


Vol.61-65 2009―2014
Vol. 65 2013―2014
No. 4
巻頭言:食材偽装表示問題と「種」の認識
特集:人類進化学の現在 人類進化学の現在:特集にあたって /人類が辿ってきた進化段階 /フローレス原人 Homo floresiensis の謎 / ネアンデルタール人と初期の現生人類の並存問題 ― 人類化石の年代推定に伴う難しさ ― /古人類のゲノム解析 ~ ネアンデルタール人とデニソワ人 / 化石から探る話しことばの起源
総説:温泉・地熱地帯は生物多様性のホットスポットか?
No. 3
巻頭言:域内研究と域外研究
特集:性決定メカニズムの多様性と進化 動植物の性決定機構概説 / 移り変わる性決定遺伝子 ― 魚類の性決定遺伝子同定からみえてきた風景 ― / 利己的な遺伝因子と性染色体進化との強い結びつき / 爬虫類における性決定様式と性染色体の進化過程 / 昆虫類の性決定 / ボルボックス目緑藻における性決定・性分化の分子機構
書評:『ダム湖・ダム河川の生態系と管理 ─ 日本における特性・動態・評価』『生命の湖 琵琶湖をさぐる』『イルカ ─ 小型鯨類の保全生物学』『私の歩んだ霊長類学』『フィールドの生物学 ─ (7) テングザル 河と生きるサル』
No. 2
巻頭言:社会的殺人としての自殺
特集:生物音響学の最前線 ─ 生物ソナー,聴覚と工学的応用 生物音響学の最前線 ─ 生物ソナ―,聴覚と工学的応用 / コウモリの生物ソナー機構 / 哺乳類末梢聴覚器の振動挙動シミュレーション / イルカのソナーと海洋生物の遠隔観測 / ゼブラフィッシュの発達過程における聴覚獲得の仕組み / ショウジョウバエの音響交信を支える神経基盤 ― 求愛歌を受容する聴覚系のしくみ ― / 昆虫における振動情報の機能解明と害虫防除への応用
総説:シカの異常増加を考える / 野生シカによる農業被害と生態系改変:異なる二つの問題の考え方
書評:『動物の系統分類と進化(新・生命科学シリーズ)』『右利きのヘビ仮説』
No. 1
巻頭言:「ゴミ化石」から探るパタゴニアと南極の植生変遷
特集:生命現象は物理学や化学で説明し尽くされるか 生命現象は物理学や化学で説明し尽くされるか / 生命現象は物理学や化学で説明し尽くされる:原理上の創発の問題における説明責任の非対称性 / 還元主義を越えて ― 生物学の多元主義的な発展像の追求 / 生命システムの通時的階層性における上位から下位レベルへの決定性 / 生命現象は物理学や化学では説明し尽くされない / 生物学的説明の二元論:生物学的文脈の中の還元論,非還元論
書評:国立科学博物館叢書 (11) 『日本の固有植物』

Vol. 64 2012―2013
No. 4
巻頭言:臨海臨湖実験所の今日的意義
特集:生物の成長と休眠 成長と休眠:特集にあたって / 概日時計により季節変動を知る高等植物シロイヌナズナの光周期依存的な生長制御 / 脊椎動物の光周性の制御機構 / 概年リズムにより内因性に制御される冬眠 / 温暖化がもたらす昆虫の成長速度の変化 / 発生タイミング制御の分子メカニズムの進化的保存性:線虫を用いた研究が明らかにしたこと
総説:生物多様性の維持機構の解明に中立理論が果たす役割
書評:『古生物学』『ナショナル・ジオグラフィックの絶滅危惧種写真集』『日本の外来哺乳類 管理戦略と生態系保全』『不死細胞ヒーラ~ヘンリエッタ・ラックスの永遠なる人生』『化学受容の科学:匂い・味・フェロモン 分子から行動まで』『レイチェル・カーソンに学ぶ環境問題』
No. 3
巻頭言:次世代シーケンサーで何ができるか?
特集:次世代シーケンサーで何ができるか? 用語解説 / 脊椎動物嗅覚受容体遺伝子ファミリーの進化研究における次世代シーケンサーの活用 / エコゲノミクスにおける網羅的遺伝子発現解析 ― 魚類での研究例から ― / 次世代シーケンサーを利用したタグによる発現解析 / 野生生物のマイクロサテライトマーカーの大量同定と保全への応用 / 生態・進化ゲノミクスのためのRADシーケンシング / 次世代シーケンサーの現状を考える
総説:アリ共生によって制限されたアブラムシの移動・分散
書評:『生態進化発生学 エコ - エボ - デボの夜明け』/『ケイン 基礎生物学(原著第4版)』/『生態学入門(第2版)』
No. 2
巻頭言:コンゴの森から
特集:霊長類野外研究の現在 日本人研究者によるアフリカにおける野生霊長類研究の過去,現在,そして未来 / 野生チンパンジーの長期研究から見えてくるもの ― 狩猟・肉食行動をめぐって ― / 同所的に生息するゴリラとチンパンジーの種間関係を探る / サバンナに生息するヒヒの研究/霊長類の社会構造の種内多様性
総説:低線量被曝の健康への影響をめぐる論争 ~ ECRRの歴史的背景 ~
書評:『海のブラックバス サキグロタマツメタ』『動物の性』『利他学』『共生細菌の世界』
No. 1
巻頭言:中国トキ事情
特集:ニッチ構築としての動物の“巣” 水の中の小さな建築者 ― トビケラ幼虫の巣の機能,構造,巣材選択の多様性 ― /リーフシェルターをめぐる生物間の相互作用:場所資源は余っているのか? / オトシブミ類の揺籃形成戦略の多様性 ― 揺籃構造と寄主植物選好性の可塑性を中心に ― / 鱗翅目昆虫のニッチとしての鳥の巣 / 森の動物の棲み家としてのキツツキの樹洞
総説:送粉生態学における動物研究の重要性:性淘汰ばかりではない生物間相互作用の面白さ ― 伊藤嘉昭(2009)への補足として ―
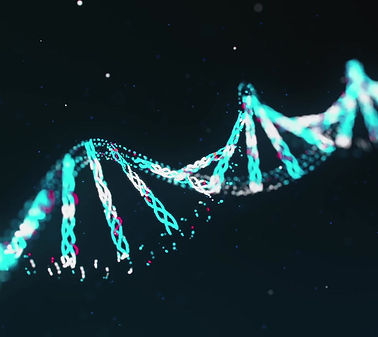
Vol. 63 2011―2012
No. 4
巻頭言:遺伝資源としての日本在来牛
特集:複合適応形質進化の遺伝子基盤 極限環境に生きる生物 そのメカニズムと応用への可能性 / 極限環境に生きる昆虫ネムリユスリカの生存戦略 / 緩歩動物クマムシの乾眠能力と極限環境耐性 / 寒冷な海に生きる魚と不凍タンパク質/寒さと生きる菌類,その凍結への適応 / 海草アマモ:海に適応した種子植物 / 強酸性土壌に棲息するアーバスキュラー菌根菌 :パイオニア植生を支える「化石的」絶対共生菌
総説:文化進化研究の現在:Alex Mesoudi 2011. Cultural Evolution : How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences. The University of Chicago Press
書評:『虫を通して森をみる ― 熱帯雨林の昆虫の多様性』『カラスの自然史 ― 系統から遊び行動まで』『魚類生態学の基礎』
No. 3
巻頭言:科学的真理の探求とそれをどう利用するかは別問題か?― 科学者の社会的責任論 ―
特集 複合適応形質進化の遺伝子基盤 特集にあたって / 兵隊アブラムシによる自己犠牲的なゴール修復 ― 分子基盤とその進化 ― / 植食性昆虫の寄主転換と種分化 / 動物の模様を「混ぜる」とどうなるか? / ぴったりとはまり合って動く関節は,どのようにできるのか?どうやってできたのか? ― 昆虫の肢の関節の発生と進化/脊椎動物が体壁に対鰭を獲得するまでの長い道のり
総説:モクズガニ類の侵略の生物学 ─ Ⅲ チュウゴクモクズガニの日本への侵入の可能性と在来種との相互作用
書評:『クワガタムシが語る生物多様性』『モグラ 見えないものへの探求心』『セックス・アンド・デス 生物学の哲学への招待』
No. 2
巻頭言:原発,風発,モデル農場
特集:植物界に見られる共通性・統一性 統一性に向けての私の歩み / 生命現象における比例関係の起源は相似とアフィン ― キクイモの成長と光合成を例にして / 植物形質のメタ解析の実用例と展望 / 植物個体呼吸のロバストネスからみた生物多様性
総説:モクズガニ類の侵略の生物学 II ─ 侵略的外来種チュウゴクモクズガニの生態学と欧米への侵略の歴史 /人類祖先の性偏向分散:種に確立された性質か
書評:『香り分子で生物学を旅する ― 嗅覚と科学のファンタジー ― 』『新しい分子進化学入門』『誰も知らない野生のパンダ』
No. 1
巻頭言:「共生と共進化」特集によせて
特集:共生と共進化 「共進化する世界」でつながる生命 / 昆虫の色や天敵からの逃れやすさが,細菌感染で変わる / 吸血性昆虫トコジラミの菌細胞内に存在する相利共生型ボルバキアの発見 / ヒル類における細胞内,膀胱内,腸内共生細菌の多様性/根粒を舞台にしたマメ科植物と根粒菌の共生
総説:モクズガニ類の侵略の生物学 / 証拠と推論の哲学:E. Sober, Evidence and Evolution
書評:『放射線リスクへの対処を間違えないために』『生命の起源を探る?宇宙からよみとく生物進化』


Vol. 62 2010―2011
No. 4
巻頭言:二つの『生物学辞典』と学術用語の定義
特集:性差と脳 脳における性差研究の現在/昆虫の脳の性差はここまでわかった / 魚類の脳の性的可塑性 / 鳥の脳 ― ヒト言語野相当領域における性差 / 味覚嫌悪学習に見られる性差 / ヒトの脳の性差をどう考えるか? ― 研究の視座から社会的意味合いまで ―/ 子守唄の生物学
No. 3
巻頭言:野外観察と大量遺伝子解析
特集 もう1つの多様性:海に生きる小さなものたち もう1つの生物多様性 ~ 海に生きるミリ未満の連虫 ~ / 深海の小さな生き物たち ― 深海性メイオベントスの生態 / 貧酸素環境の小さな生物:細胞内の小さな生物との相互作用 / ウミクワガタ類の棲息場所利用とハーレム形成 / 1ミリに住まう微生物:多様な環境,多様な機能 / 海洋生物 ― ミリレベルの優位性 / ガラモ場の葉上動物群集を調査しよう!/ こらむ:海洋における小さな共生者たち / 白海老非海老 ― 二十一世紀に蘇る公孫竜 ―
書評:『よみがえれ!科学者魂 ― 研究はひらめきと寄り道だ ― 』『マダガスカル島 ― 西インド洋地域研究入門 ―』『ザリガニの生物学』『フィールド古生物学』『あぁ,そうなんだ!魚講座』『ダーウィンと進化思想』
No. 2
巻頭言:日高さんの時代と世代
特集:追悼 日高敏隆 『生物科学』と日高敏隆 ― 断片的な実証的回顧 / 日高君と私 ― 農工大時代,動物行動学会の発足,そしてアメリカシロヒトリ / 日高さんがすぐ近くにいた時代 / 個体の来歴,ヒトの来歴 / 地球環境学と日高敏隆さん / 日高敏隆先生の業績目録
総説:ネオダーウィニズムの職人が語るネオダーウィニズムの効用と限界 / 生物多様性条約 COP10 の成果と課題 / 東北水田稲作の北方ルート伝播 / 追悼:野生動物医学における草分け 増井光子先生を偲んで
書評:『ナチュラルヒストリーシリーズ 日本の動物園』『アジアの在来家畜』『悩ましい翻訳語 科学用語の由来と誤訳』『環境倫理学』『ワークブックで学ぶ生物学の基礎』『貝類学』
No. 1
巻頭言:瀬戸内海の渚と原子力発電所 生物多様性と温暖化を調整する
特集:色と模様の生物学 チューリングパターンと動物のパターン形成:脊椎動物の皮膚模様と昆虫の翅脈パターン / トンボにおける色と模様の進化 / ショウジョウバエにおける体色と模様の進化/植物色素の排他性
総説:高校生物Ⅱの「進化」に関する教科書分析/生物多様性条約第10回締約国会議の心配事/編集委員が選んだ新入生に薦める100冊
書評:『匂いによるコミュニケーションの世界 ― 匂いの動物行動学 ―』『地球温暖化と昆虫』『理系の扉を開いた日本の女性たち ― ゆかりの地を訪ねて』
Vol. 61 2009―2010
No. 4
巻頭言:ニュージーランドと日本の森林はパラレルワールドなのか?
特集:好蟻性昆虫の隠れた多様性 好蟻性昆虫の多様性 / アリヅカコオロギ属研究の現状 / 好蟻性シジミチョウ類の多様性と進化 / オオバギ属植物幹内に共生するアリとカイガラムシ / 好蟻性昆虫の化学生態学
総説:鳥類の子殺し
書評:『保全鳥類学』『化石の記憶古生物学の歴史をさかのぼる』『昆虫科学が拓く未来』『日本の動物法』
No. 3
巻頭言:学術系インターネット:ML・ブログ・ツイッターの私的体験から
特集:生物がつくる構造物:延長された表現型 表現型”はどこまで延長されるのか / シロアリ類の巧妙な巣造りの進化 / 穴は掘るもの ― 小さなケラの巣穴周辺をめぐる諸問題 /クモの網 ― 糸と形が織りなす機能 ―/ トゲウオの巣作り:その多様性と進化 /ニワシドリ類の多要素ディスプレイ
書評:『変わる植物学広がる植物学 モデル植物の誕生』『階層構造の科学 ― 宇宙・地球・生命をつなぐ新しい視点』『擬態の進化 ― ダーウィンも誤解した150年の謎を解く』『日本の希少鳥類を守る』『生物間相互作用と害虫管理』『ニカメイガ 日本の応用昆虫学』『南極昭和基地に氷の海の生き物を見る』『動物分類学』『ザリガニ ー ニホン・アメリカ・ウチダ』『土壌動物学への招待』『新しい地球学』『昆虫の保全生態学』
No. 2
巻頭言:捕食回避か配偶闘争か:オスの配偶生存戦略の謎を解く
特集:カニの求愛行動と配偶者選択 配偶相手の時間的変化を見込んだ賢明なオスの精子配分戦略 / 性淘汰:求愛コストを実測する / シオマネキ類のセクシーな世界:Uca mjoebergi における配偶者選択,捕食,シグナルの同調性/シオマネキのウエービングで上げるはさみの高さに対する雌選択
総説:スズメを日本版レッドリストに掲載すべきか否か / 日本列島はなぜ生物多様性ホットスポットなのか
書評:『ネズミの分類学 ― 生物地理学の視点』『バイオディバーシティ・シリーズ 節足動物の多様性と系統』『子育てする魚たち ― 性役割の起源を探る ―』
No.1
巻頭言:嗅覚研究の面白さと難しさ
特集:においの生物学 嗅覚研究の生物学的意義 / 嗅覚受容体遺伝子ファミリーの進化:遺伝子数進化を中心に / ショウジョウバエの食性進化と化学感覚受容 / サクラマスで発見された性フェロモン「L-キヌレニン」
総説:イースト菌における少子化パラドックス/アブラムシ ― アリ共生関係の生態と進化
書評:『森の芽生えの生態学』『ブナ林再生の応用生態学』『干潟を考える 干潟を遊ぶ』『奇妙でセクシーな海の生きものたち』『発生遺伝学 脊椎動物のからだと器官のなりたち』『ウニ学』
