生物科学


Vol.46-50 1994―1999
Vol. 50 1998―1999
No. 4
特集:現代生物学の課題(II)進化理論と人間理解 もう一つの「サル学の現在」/人類学と人間の進化的理解/ 進化理論は心について何を語るか/ 現代分岐学の哲学と方法論へのコメント
50周年記念フォーラム(IV): 若手の成長と研究者の気概 豊かな社会の科学技術不信 / 研究者の心 / 研究に向かう原動力とは?/ 山内さんへの手紙
総説:丘浅次郎とアサジレラ
書評:『生物系統学』『チョウの調べ方』『新『人口論』生態学的アプローチ』『種の起源をもとめて』『ホミニッド』『精子戦争』
No. 3
特集:化学擬態の世界 化学擬態 ― アリをめぐる化学情報戦 ― /クモ類の化学擬態 ― ナゲナワグモは3度奇跡を起こした? ―/パートナーシップから騙しへ ― 蜂を操るランの多様な戦略―/ 生物学と記号論(II)分子水準の生物記号論:生物系において分子は記号作用する / 昆虫の生体防御の仕組み
50周年記念フォーラム(III):生物学教育 生物を忘れた生物学から生物を捨てた理科教育まで / 21世紀の生物教育
談話室:有馬朗人氏と一万円
紙碑:船越さんを偲ぶ
書評:『沖縄やんばる,亜熱帯の森』『地球を動かしてきた生命』『さよならダーウィニズム 構造主義進化講義』『臺・灣・的・蝙・蝠』『サメの自然史』『鳥はどこで眠るのか』
No. 2
特集:現代生物学の課題(I)生物学と哲学 「人間と自然の二元論」を巡る生物学と哲学の接点 / ダーウィニズムと倫理 / 生物学としての複雑系研究 / 生物学と記号論(1)なぜ生物記号論か
50周年記念フォーラム(II)第二次大戦下の生物学 戦時下の中学生と生物学 / 優生学と進化について ― 自伝的生命観の遍歴 ―/ 社会・科学・生物学 ― 生物学者の軌跡 ―/ 個体群生態学のむかしといま
No. 1
50周年記念フォーラム(I)『生物科学』の50年 『生物科学』の50年 /『生物科学』創刊のころ /『生物科学』史私論
特集:甲殻類の形態・生活史の多様性(II) ソコミジンコ類(ハルパクチクス目)の交尾前ガード /小型甲殻類の群集構造を決める要因は何か /十脚甲殻類の社会性(II)― 集団でみつかる共生性の種の個体間関係 ―/遺伝暗号の起源と進化(新説 SNS 仮説に基づいて)/ 奄美大島の自然とその保全

Vol. 49 1997―1998
No. 4
特集:甲殻類の形態・生態・生活史の多様性(I) 序 甲殻類から世界を見渡す ― 甲殻類の形態・生態・生活史の多様性 ― / 体節からわかる貝形虫類の進化 / 甲殻類の卵巣構造と卵形成様式の多様性 ― 鰓尾類チョウを例に ― /ウミクワガタ研究の現在 / フクロエビ類の移動についての謎 / 十脚甲殻類のペアで見つかる種のオス・メス関係
紙碑:八杉さんと生物科学をめぐって
書評:『総合的害虫管理』『蟻の自然誌』『アマゾンの畑で採れるメルセデス・ベンツ』
退任の挨拶:小原秀雄
No. 3
特集:植物と昆虫のインターラクション 植物と昆虫のインターラクション ― 日本における群集生態学の展望 ― / アリによる種子散布の適応的意義 / アリとカイガラムシ ― 個体群の特性に影響を与える共生関係 / ミズナラの更新パターンと動物との相互作用
総説:海洋生物資源の管理と IUCN の新レッド・リスト・カテゴリー ― とくにマグロ類をめぐって ― / 動物の形を考える ― 上皮シートの袋・階層構造・自己構築 II ―/ミトコンドリアDNAの母性遺伝 ― 精子由来のミトコンドリア DNA はどうなるのか ―
談話室:生物学を振り返る ― ISHPSSB 1997 参加報告 ―
書評:世界のオサムシ大図鑑』『スズメバチの科学』
No. 2
特集:生物多様性の保全を目指して 外なる多様性,内なる多様性 / 植物の保全生態学の今 ―「遺伝子から景観まで」を視野に入れた総合科学に ― / 日本の地域自然破壊とその保護の現状 ― 小笠原諸島を例にして ― / 多様性保護の視点からの環境保全 ― アリ群集を用いた研究例を中心 ― / 野生動物保全の新しい試み / 日本学術会議および自然保護研連について
総説:動物の形を考える ― 上皮シートの袋・階層構造・自己構築 I ―/ ナポリ臨海実験所における日本人研究者の活動
紙碑:薄井益雄 (1911 ─ 1997)
書評:『高山植物の生態』『哺乳類の生態学』
No. 1
特集:擬態の生態学 擬態再訪 / メスにのみ擬態型が現れるチョウのベイツ式擬態 / 昆虫の擬態と擬死 / スカシバガとハチ擬態 / 驚異の世界 ― ホタル擬態 ― / 魚類の種内・種間擬態/ 爬虫類における擬態 ― サンゴヘビ擬態をめぐって ― / 赤・白・黒は危険信号? ― 鳥の警告色と擬態 ―
談話室 大学博物館は Museum になり得るか?
書評:『大学博物館 ― 理念と実践と将来と ―』『野外実験生態学入門』『ダーウィンの時代:科学と宗教』

Vol. 48 1996―1997
No. 4
総説:系統学と種概念 / ドイツ語圏における社会生物学の受容過程 / リチャド・ドーキンズ 新しい構造主義進化生物学者の誕生? / アリの巣仲間認識フェロモン ― 体表ワックスによる受容と排斥 ―
No. 3
総説:日本における地生態学(景観生態学)の最近の進歩 /ムジナモの自生地外保全 / 真珠のバイオテクノロジー / 寄生虫を全地球的視野と歴史的視野で眺めよう / 非生物学専攻学生に対する生物学教育 ― 私の実践報告 ― / 革命と道化 /『われわれにとって革命とは何か ― ある分子生物学者の回想』を読んで
談話室:瞬間の記憶 ― 核問題へのアプローチ
No. 2
特集:酸性環境の生態学(II) 陸域酸性環境と植生 / ササ群落が土壌の酸性化抑制と塩基保持に果たす役割 / 日本の自然酸性湖沼と酸性河川 ― 強酸性湖宇曾利湖(pH 3.4-3.8)に分布する主な動植物と湖の歴史 ― / 陸水の酸性化と魚類 /pH 傾斜とケイ藻
書評:「金沢城のヒキガエル」
談話室:読み・書き・算盤・解剖学
No. 1
特集:酸性環境の生態学(I) 特集によせて ― 担当編集委員より ― / "酸性環境の生態学" 特集の背景と展望 / 酸性降下物が北海道の落葉広葉樹の成長に与える影響 ― マンガン過剰害を中心に ― / 酸性雨による土壌酸性化に伴うアルミニウムの溶出と,その樹木に対する影響 / 環境の酸性化とナラタケによる森林被害 / 酸性環境と地衣類 / 陸水酸性化の水生昆虫への影響について / 小さな酸性環境 ―竹の切り株の水たまりと蚊の幼虫―

Vol. 47 1995―1996
No. 4
総説:進化をつかさどる構造 / 医学領域における細菌および真菌名称の混乱 / 生物の自己増殖と論理パラドックス / 酵素反応における相補性について / 発見後 100年を経たペスト菌は今/マツ属における適応と種分化(III)― 分類群の地縁的関係と生殖的隔離 ―
談話室:農学部が失うもの
No.3
総説:魚類における自然交雑と種分化 / 溯河性回游魚による海の栄養分の陸上生態系への輸送 ― 文献展望と環境政策士の含意 ― CITES(ワシントン条約)の動向 / 遺伝暗号の起源にパラドックスはなかった(II)―ポリ tRNA 学説とその記号進化学的意義 ―
No.2
総説:海洋島の生物の種分化と絶滅 / 鰭脚類の保護区論 / 還太平洋モンゴロイドの地理的分散と言語分化(II)―コメクルド語(北米)との比較を中心として― / 動物行動の可塑性をいかに理解するか / マツ属における適応と種分化 ― 地理分布圏と分布の様相 ―
書評:『リンネと博物学 ― 自然誌科学の源流 ― 』― リネー学の金字塔 ―
No.1
総説:能動輸送の生化学再訪 / 遺伝暗号の起源にパラドックスはなかった(I)― ポリ tRNA学説とその記号進化学的意義 ―/ メンデルの遺伝子法則はなぜ成り立つのか / マツ属における適応と種分化(I)― マツ属の多様な形質と性 質― / 高等学校生物分野における STS 教育の意義と問題点 / 生化学講義メモ・その III
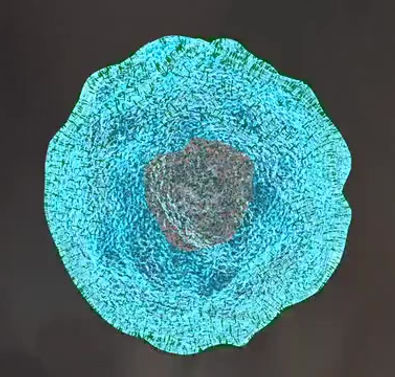
書評:
Vol. 46 1994―1995
No.4
総説:サンショウウオ科のポルノグラフィーはどこまで描けたか / 対称性のゆらぎとメスの選り好み / 人工衛星を利用した野生動物の移動追跡 / 進化論とアメリカのファンダメンタリズム/ 分類学は学問ではないのか? ― 利根川進氏の分類学観に対する疑義 / 生化学講義メモー(II)
No.3
総説:丘浅次郎先生の面影 /生殖細胞の死と救助技術--研究の到達点と種存立における意味 / 生物分類におけるスプリッティングとランピング / 生化学講義メモーI / ベトナムにおける新種野生動物の発見 / なぜ "more than" を誤訳するのか? / 太田論文をめぐって ― 誤訳問題と論争のマナー
No.2
特集:植食性テントウムシの生物学 エピラクナ,研究対象としての魅力 ― 小特集の編集にあたって ― /オオニジュウヤホシテントウ群と「種の問題」/ トホシテントウの寄主利用 ― 食植性昆虫の寄主選択 / ニジュウヤホシテントウの休眠誘起 / インドネシアのマダラテントウ類の生活史と個体群動態
総説:オマキザル類の社会 / 老化・老衰の関数法則 ― ネビの概念とともに / ヤドカリ類の闘争行動に関する近年の研究の発展 (II) 貝殻闘争,儀式化の進化
No.1
特集:新世界ザルの社会構造--旧世界ザルとの比較から 霊長類社会の新世界 / 新世界ザルの社会構造の進化 / クモザル亜科の社会 / クモザル亜科と類人猿の社会進化 / オマキザルの雌雄は何をめぐって争っているのか ― オナガザルの母系的社会との比較 / 新世界ザル特集とマカレナ調査地

書評: