生物科学
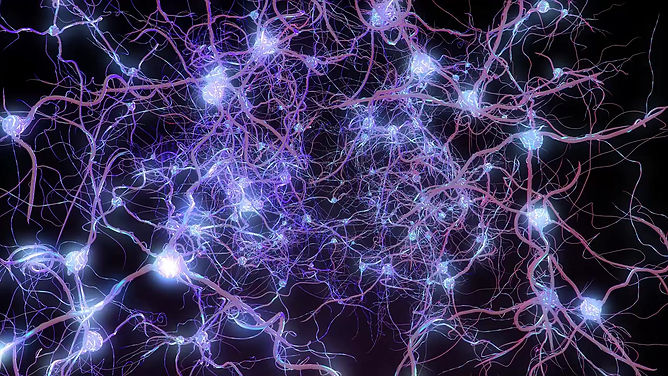

Vol.26-30 1974―1978
Vol. 30 1978
No. 4
巻頭言:本誌 30巻をふりかえって
特集:本誌30巻を記念して 八杉龍一 ; 碓井益雄 ; 秋元寿恵夫 ; 沼田真 ; 柴谷篤弘 ; 柳田為正 ; 江上不二夫 ; 鈴木直治 ; 真船和夫 ; 原田市太郎 ; 福島要一 ; 永野為武 ; 南博 ; 林雄次郎 ; 中谷林太郎 ; 森主一 ; 渋谷寿夫 ; 柴岡孝雄 ; 永井進 ; 檜木田辰彦 ; 都留信也 ; 野沢洽治 ; 鈴木善次 ; 小原秀雄 ; 和気朗 ; 新田毅 ; 丸山芳治 ; 斎藤光生 ; 安東民衛 ; 川口啓明
総説:生物学と GOETHE の urbildliches Denken / 栃木県北部におけるシカ・ツキノワグマの生息状況と大物猟の動向
生物教育シリーズ VIII:高校生物教育にかんする大学教員の意見
談話室:'Protobiont' と ‘Probiont'
No. 3
総説:ヒトの消化管に棲む"絶対嫌気性"細菌と O2 との関係 /オペラント条件づけを利用したラット学習行動観察方法 / 植物における遺伝的矮性の発現機構 ― その生理的側面
論点:神経伝達物質の放出のメカニズム--シナプス小胞仮説をめぐる論争 / シナプス小胞仮説の成立 / 小胞仮説の生化学的検討 / 伝達物質の放出とシナプスの微細形態
生物教育シリーズ VII:生物教育の課題と問題点
談話室:教壇を舞台に
総説:根粒バクテロイドは増殖能をもつか?
書評:『ダーウィン再考』
No. 2
特集:生物現象の階層性 発生現象の階層性 / 生物界の構造についての一つのコメント / 生物系の論理と研究方法 / 生物的自然の階層構造論をめぐって / 医学における階層性
生物教育シリーズ VI:混迷を深める高校生物教育
総説:高等植物の生長と起電的活性と代謝 ― 静止電位をゾンデとして
書評:『個体の行動』
No. 1
特集:霊長類における性の進化 性の進化史的意義とヒト化の問題 / 性的二型試論 / 哺乳類の性周期 ― ホミニゼーションにかかわる視点から / 霊長類の性的二型 / 初期人類における道具製作と性的二型 / 霊長類の社会構造における性 ― ヒトの家族の起原に関して / 男と女にみられる性の社会的役割 / 霊長類のなかの性事
生物教育シリーズ V:高校生物教育についての二三の意見
総説:卵の大きさはいかに決まるか/Ricca's factor
書評 :『Transport in Plants II』『生物と機械の間 ― 生物工学入門』『科学と生物教育』『植物生理学』

Vol. 29 1977
No. 4
総説:ペントース・イソメラーゼ群の進化(仮説) ― 基質特異性の分化について / カエルにおける種の問題 / ペスト菌のジデロクロム産生とウイルレンスとの関係 ― 続・ペスト菌と動物体と鉄 / アルミニウムの植物に対する生理作用 / 電気魚発電器官のシナプス小胞
生物教育シリーズ IV:定時制高校での生物教育 ― ひとつの体験
No. 3
総説:ツメガエル卵の受精過程と多精拒否機構 / 食うものと食われるものの相互作用系の解析 / サイトカイニンの作用機序
生物教育シリーズ III:高校の生物教育と大学の生物学
総説:生活史の起源 (II) 新しい生活史学のための覚書き / アロステリック酵素のサブユニット相互作用 (II) 反応速度論による考察
論点:鷲谷・佐藤博士の「鉛塩沈殿による酸性フォスファターゼの細胞内分布検出方法の検討」を読んで思うこと
談話室:第24回日本生態学会印象記(広島 1977) /cyclic GMP 研究の現状について
書評:『Lysosomes in Biology and Pathology 5』『Integrated Control of Weeds』『The Lytic Compartment of Plant cells』『The Golgi Apparatus』
No. 2
総説:生活史の起原 (I) 新しい生活史学のための覚書き / 行動科学的にみたプラセボ効果の発現機序について / アロステリック酵素のサブユニット相互作用 (I) 反応速度論による考察 /
全多様度,平均多様度および相対多様度 / アメリカヤマゴボウからの光合成光化学系粒子の単離について / ラン科植物の胚のうについて / 等価変換の考え方と生物学 (II)/ 進化・適応・生存競争の種々相 (V)
書評:『Allgemeine Geobotanik』
No. 1
総説:等価変換の考え方と生物学 (I) / 鉛塩沈殿による酸性フォスファターゼの細胞内分布検出方法の検討 / 生体の非特異的防禦機構を担うインターフェロン / 関東地方におけるシカの分布 ― アンケート・ききとり調査による
生物教育シリーズ II:教育課程改定から新教科書採択まで ― その制度的機構
特集:ホミニゼーション II バンブティ・ピグミーと蜂蜜 / ブッシュマンのサブシステンス--その進化史的考察
書評 :『Wörterbücher der Biologie - Ökologie』『Ostracoda』『色素細胞』『Strasburger's Textbook of Botany』

Vol. 28 1976
No. 4
総説:HLA 抗原 / エビ・カニの体色をめぐって (II) /高等生物の遺伝子の構造 (III) / 進化・適応・生存競争の種々相 (IV)
生物教育シリーズ I:高校生物教育の現状と問題点に関する一考察
特集:ホミニゼーション I:人類の適応と進化 / 霊長類の食性・遊動パターンと社会 /人類の適応とその限界
談話室:無脊椎動物の免疫現象
書評 :『植物ホルモン』『Phloem Transport』『ヒトと微生物のたたかい』
No. 3
総説:コケ植物の起源と進化をめぐる諸問題 / 群馬県におけるカモシカの分布 ― アンケート・聞きこみ調査による / エビ・カニの体色をめぐって (I) /生物界の階層を求めて / 高等生物の遺伝子の構造 / 進化・適応・生存競争の種々相
理論生物学・数理生物学講座 XIII:繰返し型の成長を記述する言語
談話室:霊長類学と博物館 ― 日本モンキーセンター事件の背景 / セルラーゼの細胞内分布
書評:『サンバガエルの謎』『Migration and Homing in Animals』『溶原性』『DNAと染色体』
No. 2
総説:生物界の階層を求めて I /高等生物の遺伝子の構造 (I) /コムギにおける低温処理効果の累積について / イネの環境反応と適応性 ― とくに北方イネと南方イネの生態を中心として/ イネ子葉鞘の生長に対するフィトクロームの作用 / 進化・適応・生存競争の種々相 (II) / 生体の機能とシステム的考察 ― 不可逆過程の速度論より
理論生物学・数理生物学講座 XII:ピュッター・ベルタランフィ成長モデルの検討 (I) 方程式の解析
談話室:和欧文による発表の場を持とう / 植物にも免疫はあるか?
書評:『進化をどう理解するか』『生体膜と生体エネルギー』
No. 1
特集:霊長類と食虫類・翼手類の系統・進化 まえがき / 最近の原始哺乳類化石研究の動向 / 食虫類の生態 / 翼手類の系統分類 / 翼手類の系統論への機能形態学的アプローチ,とくに飛翔に関して / 食虫類,翼手類,霊長類(原猿)における進化的考察-― とくに脳と特殊感覚(聴覚)を中心として / 大脳化か新脳化か / ツパイ (Tupaiidae) について/ コモン ツパイ(Tupaia glis)の上肢の筋について ― 食虫類,原猿類との比較研究
談話室:第12回国際植物学会
書評:『Residue Reviews Vol. 54』

Vol. 27 1975
No. 4
特集:植物実験分類学をめぐって セイタカアワダチソウの生活史 ― 個体群動態からのアプローチ / カシワバハグマ類(キク類)の種とその類縁 / 日本海要素の生態学的研究 / タンポポ属(Taraxacum)の侵入と定着について / 多年生草本の生長解析
総説:進化・適応・生存競争の種々相 (I) /懸賞論文制度の紹介
書評:『Coupling of Land and Water Systems』『減数分裂』『動物分類学の基礎』
No. 3
総説:ホルモン リセプターと Radioreceptor assay / 睡眠・覚醒リズムと成長ホルモン分泌 ― 動物実験モデル開発の試み / 植物におけるペントースリン酸経路の生理的意義と調節機構 /ミツバチ女王蜂の分化と王乳 /イノシシおよびシカの捕獲と植生区分 ― 京都府における調査から
書評:『植物の休眠と発芽』『ミトコンドリア』『生きものと放射線』
No.2
特集:生命の起原 地球大気の進化 / 原始地球における有機物の生成と進化 / 化学進化における多分子系 / 始原生物の発生 ― 地質学古生物学からのアプローチ / 化学化石における二,三の問題 / 細胞の起原に対する一考察
総説:近畿地方におけるイノシシ,雄ジカの生息面積とその密度 ― 1972年度出猟実態調査による
理論生物学・数理生物学講座 XI:個体成長の古典的モデルとダイナミカルシステム
書評:『神経興奮のメカニズム』
No.1
総説:細胞表面糖タンパク質 / 自己増殖オートマトン分子生物学 / 藍藻類の分類形質についての考察 / コムギを中心とした栽培植物の起源 / ニホンザルの集団遺伝学
書評・新刊紹介 :『Ökophysiologie der Pflanzen-Reihe.Bausteine der modernen Physiolosie』『Temperature Regulation in Mammals and Other Vertebrates』『海洋動物生理』『染色体によらない遺伝』『現代生物科学』『動物の色の生物学的意義』

書評:
Vol. 26 1974
No. 4
特集:アウストラロピテクスとその周辺 初期人類の形態特徴とその適応的意義 / アウストラロピテクスの文化 /イツリの森の物語 /歯からみたアウストラロピテクスの進化上の問題 / 猿人の年代学的背景 ― 最近の研究成果から
理論生物学・数理生物学講座 X:自殖集団の数学理論 ― 特に対称性の観点から (II)
総説:アメーバ表面の酸性多糖質
No. 3
総説:細菌の胞子形成の制御機構 /車軸藻類における核型の研究 /動物保護の諸問題
談話室:ボン大学動物教室
理論生物学・数理生物学講座 IX:自殖集団の数学理論 特に対称性の観点から (I)
書評・新刊紹介:『Temperature and Life』『Protozoology』『生産生態学のミステリー』『Advanced Techniques in Biological Electron Microscopy』
No. 2
総説:蛋白合成における Wobble - pair の役割仮説 / 葉序の起源と確率過程 / γ進化からみた生物の繁殖戦略と生活史 Cole の命題に関連した一般理論 (I) / 湖沼のミクロフローラとその地球化学作用 クズネツォフの著書を中心とした水圏微生物学の紹介(抄録)(III) /筑波移転反対運動と医用霊長類センター建設計画 / ヒエ・キビ・アヅキ その民族植物学的考察
談話室:浦島太郎の愛国主義
理論生物学・数理生物学講座VIII:生物システムの関係構造 (II)
書評:『森林の生態』
杏林大学学則改悪に抗議する
No. 1
総説:量子生物学は将来生物学の分野において市民権を獲得できるか? / RNA の限定分解の生物学的意義に関する一考察 / 土壌重金属汚染地帯における植物の生育・重金属吸収反応に対する種特異性 / ニホンカワウソの衰退を辿る 主に四国のカワウソについて / アンモニアによる植物の代謝異常の一断面 ― 続 ― /J. MONOD 著,渡辺格・村上光彦訳“偶然と必然”を読んで /カジノキ,ワタおよびアダンに関する民族植物学的考察 / 湖沼のミクロフローラとその地球化学作用 クズネツォフの著書を中心とした水圏微生物学の紹介(抄録)(II)
談話室:動物行動学について
書評:『海洋の生態代謝』『動物の呼吸―比較生理学的展望』『生物学の歴史』『生物系統 学― 理論と方法』『動物界の階層 ― 分類の方法と原理』

書評: