生物科学


Vol.11-15 1959―1963
Vol. 15 1963
No. 4
提言:和文学術雑誌について
総説:石油微生物学の最近の進歩 (I) /動物のセルラーゼ / 芳香環生成におけるシキミ酸代謝 / チョウの季節型とその決定要因 / 方法論雑稿 IV. 発生学における比較的方法 /大学一般教育課程の生物学の内容について II
基礎生物学シリーズ 3:植物における物質の転流
講座:生物学と比較 IV 行動学における比較
談話室:生物学における説明 ― とくに目的論的説明について
生物科学研究連絡グループ(仮称)の結成について
本誌定価の改訂について
No. 3
総説:無機窒素代謝の酵素化学 最近の進歩から / オジギソウの運動に関する細胞・組織生理 (II) / 植物しゅようの生理 (II) / 日本の生態学 批判的考察 (II) /方法論雑稿 (III) 方法論から発見学へ / 高校教育課程における生物学の問題点とその対策 / 大学一般教育課程の生物学の内容について (I)
講座:生物学と比較 III 形態学と比較
書評:『Animal Ecology, Aims and Methods』
No. 2
提言:解説書の手法について
総説:オジギソウの運動に関する細胞・組織生理 I / カサノリの細胞分化と核細胞質関係 / 植物学上の用語「生長」について / 生態学における表面現象 ― 水面昆虫の物理化学 II / 日本の生態学 ― 批判的考察 I /方法論雑稿 II. 機械論とは何か / ふたたび IBP (International Biological Programme) について
講座:生物学と比較 II 生化学と比較
談話室:アメリカの歴史学者ジョラフスキー氏のルイセンコ問題分析について
書評:『昆虫における訪花性の起原』『Introduction to Soil Microbiology』
No. 1
提言:学会の解体再編制を提唄する
総説:植物しゅようの生理 (I) その呼吸 / 生態学における表面現象 水面昆虫の物理化学 (I) / ソビエトの魚類生態学についての覚え書き / 日本の放射線生物学 (II) 村地教授の足跡 /花成研究の一断面 ダイズにおける早晩性の解析 / 方法論雑稿I-方法論のすすめ / 生物物理と生物学
講座:生物学と比較 I 比較の方法はもう古いのか?
書評:『Experiments in Genetics With Drosophila』『抗生物質の話』『人間の宇宙生活』
紹介:生化学若い研究者の会・夏の学校 /ソビエト科学についての議論

Vol. 14 1962
No. 4
提言:大学一般教育課程の生物学教育
総説:節足動物媒介ウイルスについて 昆虫学の立場から / 硫黄化合物の代謝 -(II) /インフルエンザワクチンをめぐる一つの研究方向 / 日本の放射線生物学回顧と展望 / 中村禎里氏に対する反批判
基礎生物学シリーズ 2 生物とエネルギー
講座:個体群生態学 IV 実験個体群
談話室:ソビエトでの生命論
書評:『図説・地球の歴史』
紹介:『昆虫の光周性と生活環」/ IBP (International Biological Programme) について / どこへ留学するべきか ― J. B. S. HALDANE の助言
No. 3
提言:科学者京都会議の声明について
総説:硫黄化合物の代謝 (I) / 大気汚染とくにスモッグに対する植物の反応 / 秋播型禾穀類の発育生理とジベレリン / 細胞の微細構造
講座:個体群生態学 III 野外における動物個体群の研究例
談話室:ほんとうのことをはっきりと ― 大衆が科学者にのぞむこと / 科学者も政治の中に生きている
書評:『日本農業の反省』『イネの栄養生理』『社会生物学入門』『生命の歴史,進化の意味』
No. 2
提言:曲り角の農業と研究管理
総説:円口類と板鰓類の副腎系 / 細胞分裂と代謝系の働き / 弛緩因子の作用機構 / チョウのサナギの色彩適応 / イネの進化学史 (II)
講座:個体群生態学 II 統計的操作
談話室:スエーデンの大学制度について
書評:『動物の行動』『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』『動物生態学』
No. 1
提言:日米科学合同委員会と学術会議の態度
総説:溶原性と形質導入をめぐる諸問題 / 青酸の作用 / 接木雑種の基礎的な実験と問題点 / 湖沼における植物プランクトンの生産と栄養塩の動きについて / ホルモンの作用機構についての新しい仮説
講座:個体群生態学 I 個体群調査法
談話室:私の科学革命観
紹介:『フランス百科全書の研究』
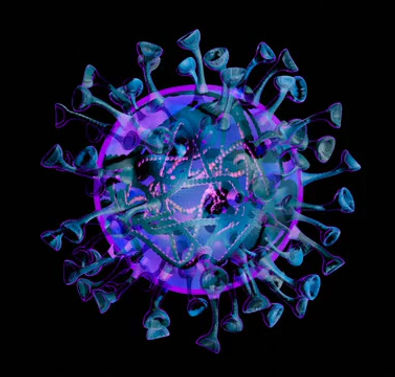
Vol. 13 1961
No. 4
巻頭言: 小児マヒ問題から学んだもの
総説:生態遷移における問題点 / Burnet の思想と免疫学の進歩 / F. M. Burnet の業績についての一考察 / インシュリン分泌の神経性調節 (II) / 民主主義科学者分解の秋にあたり最悪の方針が提出された―柴谷説批判 / 生物学における研究体制の現状分析と改善策
講座:ホルモン IV 神経分泌
談話室:アマゾンへの留学
書評:『科学研究の態度―成功の要点』『C. A. VILLEE ‘Biology‘』『自然と生命のパレード』
紹介:科学論・生物学方法論の近著
No. 3
巻頭言:生物学者と社会的責任
総説:脳の機能と物質的痕跡 / 環境制御下におけるイネ・ムギの生育型の解析 /インシュリン分泌の神経性調節 (I) /アメリカ医学の危機 / 生物・化学兵器の現状 ― その全面的禁止実現のために ―
講座:ホルモン III 植物ホルモン
談話室:ドイツ人の研究態度の底を流れるものの1つ
書評:『ダーウィン進化論百年記念論集』『体系学習・生物』
No. 2
巻頭言:昆虫学のメタモルフォーゼのために
総説:能動輸送の生化学的研究 ― Carrierの問題を軸として / アカヤドリコバチ群の寄主選択の研究 ― とくに寄主選択と種の分化の問題について (II) /腫瘍細胞の核小体数 ― ただ一つ変らざるもの / 昆虫類の系統学的研究の一指標としての消化管の形態について / 生物学革命と生物学者の科学運動(II. 生物学者の科学運動)
講座:ホルモン II 昆虫のホルモン
談話室:カール・ベール(フォン・ベア)の生涯と思想
書評:『血液―あなたの生命を左右するもの』『集団遺伝学概論』
No. 1
巻頭言:生物学攻略の綜合的方策をもとう
総説:オーキシン作用と細胞壁―とくに原形質の役割 / アカヤドリコバチ群の寄主選択の研究 ― とくに寄主選択と種の分化の問題について (I) /硬骨魚類の副腎 ― その形態と機能 /イネ科における亜科の分化と発芽生理学的特性との関係 / 生理学革命と生物学者の科学運動(I. 生物学革命)/ 系統学の立場
講座:ホルモン I 内分泌学の諸問題
談話室:心霊現象の分析と対策
書評:『進化の分子的基礎』『生命の内幕』
紹介:『科学技術者』『La Spéléologie』
民科蚕糸技術研究会のあゆみ
民科生物学部会総会の報告
民科生物学部会声明

Vol. 12 1960
No. 4
総説:蛋白質の生合成―絹フィブロインの生合成をめぐって / プラナリアの再生における極性と頭尾分化の問題 ― 双頭形成を中心として / 古生物学における‘種'の問題についての管見 / 脊椎動物の社会構造 ― 特に生産について(つづき)/ 中学校の生物教育 / 高校の生物教育とその問題点 / 小滝氏の論文をよんで
講座:癌 IV 癌細胞の燐酸代謝 ― 特に酸溶性燐酸化合物の代謝(つづき)
談話室:思いつくまま ― 佐藤氏の批判に答う
書評
No.3
総説:植物の組織培養 /食植性昆虫の寄主選好における化学物質の役割 /脊椎動物の社会構造 /人類学の立場からみた皮下脂肪研究/ 水稲育種のアウトサイダー
講座:癌 III 癌細胞の代謝 ― 特に酸溶性燐酸化合物の代謝 ―
談話室:生物学者も工学研究室へ進出せよ
紹介:A. N. SEVERTZOV 記念動物形態学研究所
書評
No.2
総説:家畜育種における遺伝と環境 / 近代遺伝学の諸問題 /人為的同調分裂 /種の分化/微細複対立遺伝系の中からホモ接合体を固定する理論の実験的基礎 / 日本の基礎生物学の問題点 (III) /心理学と社会
講座:癌 II 発癌問題におけるウィールス性腫瘍の立場への一考察
談話室:中国における植物生理学の十年間
書評
No.1
総説:近代生物学成立史・試論 / 日本の基礎生物学の問題点 (II) / 昆虫におけるアセチルコリンの存在について
講座:癌 I 腫瘍組織の異種移植について / 癌発生の機転の諸問題
紹介:高等生物の人為型転換 / 第10回民科生物科学シンポジウム報告
書評

書評:
Vol. 11 1959
No. 4
総説:フェノールによるリボ核酸の分別 /生態的地位を等しくする2種類の動物個体群の野外での共存について / 蝶類の地理的変異の分類に対する基礎論 (II) / Chemical Systematics への諸問題 (III) / 適応の諸問題 /形態形成に関する Rose の理論 / 日本の遺伝学と見波定治 / 生物学における基礎と応用との関連について /日本の基礎生物学の問題点 (I)
書評
No. 3
総説:細胞核の生理的意義 / 細菌の形質変換 / 蝶類の地理的変異の分類に対する基礎論 (I) /長崎市内一病院における新生児先天奇形の頻度について
生物教育の諸問題:生物教育と生物教材 / 大学入試からみた高校の生物教育 / 生物学と生物教育 / 総合討論
科学教育研究協議会について
本年度民科生物部会シンポジュームのお知らせ
No. 2
総説:生理学の進歩と最近の傾向 / 動物分類学の傾向と動物記載学の重要性 / 高等植物のチトクローム / 生活を通しての生物進化 / 生物学における場の理論 / Chemical Systematicsへの諸問題 (II) / スミレ類の観察 / 昆虫の休眠性の地理的変異
談話室:大学院制度雑感 /本誌 10巻 4号 の森下氏の意見について
書評
No. 1
総説:魚類腎臓の構造と機能 / 情報理論の考え方と生物学 / 発生学における形態の問題 / 脊椎動物の社会構造 / 植物体上における性の分化と生理 / 植物葉中にふくまれる成分含量の内的変動にかんする一考察
書評

書評: